はじめに
財産・相続の整理は、家族に負担をかけず、相続トラブルを防ぐために重要な終活の一部です。
この記事では、財産の棚卸し方法、生前贈与の活用、遺言書作成など、相続トラブルを防ぐための具体的な整理方法と注意点を詳しく解説します。
財産・相続の整理とは?
財産・相続の整理の目的
財産・相続の整理とは、自分の財産を把握し、相続税対策や相続トラブルを未然に防ぐための準備を進めます。
- 相続税の負担を軽減する
- 遺産分割での家族間トラブルを防ぐ
- 相続手続きをスムーズに進める
財産・相続の整理を開始するタイミング
50代から60代で準備を始めるのが理想的です。 特に、以下のタイミングで意識すると良いでしょう。
- 安心の結婚や独立を機に財産の整理を始める
- 退職後に本格的な終活を開始します
- 相続税対策を意識する場合は、早めの生前贈与を検討する
財産の棚卸しの方法とポイント
財産の種類を把握する
次に、自分の財産をすべてリストアップすることが基本です。以下のような財産を確認しましょう。
✅金融資産(預貯金・株式・投資信託)
✅不動産(土地・住宅・別荘)
✅貴金属・美術品(骨董品・宝石・コレクション)
✅保険(生命保険・年金保険)
✅権利(ローン・借金)
財産の棚卸しの手順
1.財産の種類ごとにリストアップする
- 口座銀行、証券口座、不動産の権利証を確認
- 保険証券、年金の受給証書を整理する
2.課題も正確に認識する
- 住宅ローン、カードローン、借入金を確認
- 借金がある場合、相続放棄の可能性も考慮
3.評価額を確認する
- 不動産は固定資産評価額を確認
- 株式は最新の株価を確認
4.エンディングノートに考える
- 財産リストを終えるノートに考えることで、相続人が分かりやすくなります。
生前贈与の活用で相続税対策する
生前贈与とは?
生前贈与は、生きているうちに財産を分けることを考え、相続税対策として有効です。 特に、相続税の基礎控除額が考慮された今、早めの対策が重要です。
生前贈与の種類
- 暦年贈与(毎年110万円まで非現金)
- 相続時精算金銭制度(2,500万円まで贈与税がかからないが相続時精算)
- 住宅資金取得贈与の特例(最大1,000万円まで非現金)
生前贈与のポイント
✅贈与契約書を作成し、記録を残す
✅銀行振込で贈与の証拠を残す(現金手渡しは心配)
✅毎年110万円以下の贈与をコツコツ行うことで、相続税の対象財産を減らす
遺言書作成と法的有効力の確認
遺言書種類
- 公正証書遺言:公証役場で作成、法の有効力が強く確実
- 自筆証書遺言:自分で書く遺言、手軽だが法的なリスクがある
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人が保管
遺言書作成のポイント
✅法的に有効な形式で作成する(日付・任意・押印が必要)
✅遺留分を適当にして決める(相続人の最低限の取り分)
✅遺言執行者を指定しておく(相続手続きを代行する人)
相続税のシミュレーションと対策
相続税の基礎知識
- 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 現金対象の財産:現金・預貯金・不動産・株式など
相続税対策のポイント
✅生命保険の活用(死亡保険金の非金銭枠を活用)
✅不動産の評価減対策(貸家や貸地にすることで評価額を下げる)
✅生前贈与で相続財産を減らす
財産・相続の整理で失敗しないための注意点
⚠名義名義に注意→贈与したつもりが相続税の対象になる可能性がある
⚠遺言書内容に矛盾があるか確認
⚠相続人間での判断を早めに行う、トラブルを未然に防ぐ
まとめ
財産・相続の整理は、早めに行うことで家族の負担を減らし、相続トラブルを防ぐことができます。
- 財産の棚卸しを行い、正確な財産リストを作成
- 生前贈与を活用して、相続税の負担を軽減
- 遺言書を作成して、遺産分割を明確化
- 相続税のシミュレーションを行い、事前に対策を講じる
まずは、財産の棚卸しから始めて、家族としっかり話すことが大切です。
専門家(税理士・司法書士)に相談しながら、計画的に進めていきましょう!

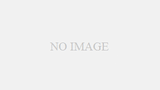
コメント