はじめに
逝去直後の初日〜3日目は、最も早く早く、感情が動きやすい時期です。
しかし、この期間にやるべき手続きや連絡が多く、特に初めての経験では何から手を付ければ良いのか戸惑うことが多いのではないでしょうか。
この記事では、逝去直後の1日目〜3日目の初動対応の流れ、な手続き一覧、必要書類、関係者への連絡方法、葬儀社の手配、注意点を詳しく解説します。
逝去直後の1日目〜3日目の初動対応が必要な理由とは?
当面で多くの手続きを行う必要がある
逝去直後の1日目〜3日目は、死亡診断書受け取り、搬送準備、届出の提出、火葬許可証の取得、関係者への連絡、葬儀の準備など、当面で多くの手続きを迅速に行う必要があります。
特に、死亡届の提出期限は死亡後7日以内のため、早めの流れを把握しておくことが大切です。
手続きの漏れやトラブルを防ぐ
- 手続きの種類が多く、関係者への連絡が必要なため、手続きの漏れや連絡漏れが起こりやすいです。
- 事前にチェックリストを作成し、必要な手続きを確認しておいてください、手続きの漏れやトラブルを防ぎます。
家族の負担を軽減できる
- 逝去直後は精神的に動いていることが多いため、事前に流れを確認しておいて、家族の負担を軽減できます。
- 役割分担を決めるために、スムーズに手続きを進められるために、事前に家族間で共有しておくことが大切です。
逝去直後の初動対応の流れ【1日目〜3日目の基本的な流れ】
1日目の流れ
- 医師からの死亡診断書を考える
- 葬儀社に連絡して搬送を手配する
- 搬送先(自宅、斎場、葬儀会館)へ搬送する
- 家族・親族への連絡
2日目の流れ
- 死亡届の作成
- 死亡届の提出(市区町村役所)
- 火葬許可証の取得
- 葬儀の日程と場所の確認・予約
3日目の流れ
- 関係者への連絡(友人、友人、職場)
- 葬儀の準備(祭壇の準備、遺影写真の準備)
- 通夜・告別式の段取り確認
- 返礼品・香典返しの準備
1日目に行うべきこと一覧【死亡診断書受取・搬送手配】
死亡診断レポート
✅医師からの死亡診断書を受け止めて
- 死亡診断書は、死亡届の提出や火葬許可証の取得が必要です。
- 原本とコピーを保管しておき、役所手続きや保険請求に使用します。
✅死亡診断書内容確認
- 故人の氏名、年齢、死亡日時、死亡場所、死亡原因が正確に記載されているか確認します。
- 記載ミスがある場合は、医師に修正を依頼します。
葬儀社への連絡と搬送手配
✅葬儀社への連絡
- 事前に決めていた葬儀社に連絡し、荷物の伝達を依頼します。
- 搬送先(自宅、斎場、葬儀会館など)を事前に確認しておくと、迅速に対応できます。
✅搬送の流れ
- 葬儀社に連絡して搬送車を手配
- 病院・施設から指定された場所で受け取りの引き渡し
- 搬送先へ移動(自宅、斎場、葬儀会館など)
2日目に行うべきこと一覧【死亡届の提出・火葬許可証の取得】
死亡届の作成と提出
✅死亡届の作成
- 死亡診断書と一体化している死亡届には、必要事項を記入します。
- 届出者の意思・押印が必要なため、印鑑をご用意します。
✅死亡届の提出
- 提出先:市区町村役所の戸籍課
- 提出期限:死亡後7日以内
- 火葬許可証が発行され、火葬・埋葬に必要なため、必ず受け取り、保管します。
まとめ
逝去直後の1日目〜3日目の初動対応を事前に確認しておいて、黙らずに対応でき、家族の負担を軽減することができます。

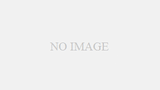
コメント