はじめに
今年、「終活」という言葉が広まり、多くの人が生前のうちに自分の財産や葬儀の準備を進めています。終活を早めに行うことで、家族の負担を減らし、相続トラブルを防ぐことができます。
この記事では、生前やるべき準備を「財産管理」「医療・介護」「葬儀の準備」の観点から詳しく解説します。
終活とは?
終活の目的
終活とは、自分が亡くなった後に家族が難しくないように、生前に準備を進めることを向きます。 主の目的は以下の通りです。
- 家族の負担を軽減(葬儀・相続手続きをスムーズにする)
- 財産の分配を明確にする(相続トラブルを防ぐ)
- らしい最後を迎える(葬儀やお墓の希望を伝える)
終活を始めるべきタイミング
終活は早めに始めるのが理想的ですが、特に以下のタイミングで意識すれば良いでしょう。
- 50代:財産整理・相続対策の検討を開始します
- 60代:医療・介護の方針を決める
- 70代:具体的な遺言書やエンディングノートを作成
生前にやるべきこと(終活のポイント)
終活には、大きく分けて以下の3つの準備が必要です。
- 財産管理と相続準備(財産の棚卸し、生前贈与、遺言書作成)
- 医療・介護の意思決定(延命治療の希望、介護方針の決定)
- 葬儀・お墓の準備(葬儀の形式・お墓の選定)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
財産管理と相続準備
財産の棚卸し
次に、自分の財産をリストアップしましょう。 主な財産の種類は以下の通りです。
✅金融資産(預貯金・株式・投資信託)
✅不動産(土地・住宅)
✅収益(ローン・借金)
財産を整理しておりますので、相続時に何をどのように分配するか明確にできます。
生前贈与の活用
生前に財産を考えることで、相続税の負担を軽減できます。
- 暦年贈与(年間110万円まで非現金)
- 相続時精算金銭制度(2,500万円まで贈与税がかからないが相続時精算)
- 住宅資金取得贈与の特例(最大1,000万円まで非現金)
贈与の際は、契約書を作成し、銀行口座に証拠を残しておくことが重要です。
遺言書作成
相続トラブルを防ぐために、遺言書を作成しましょう。
- 公正証書遺言(公証役場で作成するため法的に有効)がおすすめ
- 自筆証書遺言(簡単に作成できるが、有効になるリスクがある)
遺言書には、財産の分配方法や遺言執行者(訴訟を行う人)を確実にすることが重要です。
医療・介護の意思決定
延命治療の希望を決める
- 延命治療を希望するかどうかを決め、家族に伝えておく
- 賢死の意図がある場合、「リビングウィル」を作成する
介護の方針を決める
- 施設入居か在宅介護決定
- 介護費用の準備(公的支援や民間サービスを活用)
葬儀・お墓の準備
葬儀の形式を決める
- 家族葬・一般葬・直葬(火葬のみ)などから選択
- 参加者の範囲を決めておく
お墓の選択
- ここのお墓に入るか、新しく準備するか決める
- 永代供養や樹木葬など新しい供養方法も検討
エンディングノートの活用
エンディングノートに記録すること
✅財産情報(知人・不動産・保険)
✅葬儀やお墓の希望
✅医療介護・の意向
✅家族や親族へのメッセージ
エンディングノートは法的な有効性はありませんが、遺言書と併用することでスムーズな手続きをサポートできます。
まとめ
終活を早めに始めることで、家族の負担を減らし、自分の希望を叶えることができます。
🔹財産整理・生前贈与を活用し、相続対策を進める
🔹延命治療や介護の方針を決める
🔹葬儀・お墓の希望を家族と共有する
🔹エンディングノートで計画を記録する
終活は「まだ早い」と思いがちですが、早めに準備することで安心して人生を過ごせます。
それでは終わりノートの作成や財産の棚卸から始めてみましょう!

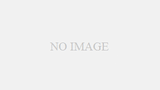
コメント